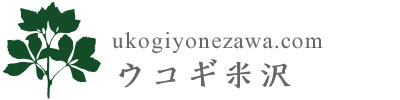- ホーム
- 米沢のウコギ
米沢のウコギ

兼続が米沢に持ち込み、食用を兼ねたかき根として鷹山が奨励
- ウコギとはウコギ科の植物で、米沢地方では古くから食用を兼ねた垣根として利用されています。
- 上杉の知将「直江兼続公」にて米沢で栽培が始まり、後の米沢藩九代藩主「上杉鷹山公」がウコギの垣根を奨励したとされ、春から初夏にかけての新芽が美味しく切り和えやおひたしをはじめ天ぷらなど、様々な料理法でいただけます。
ウコギのルーツ
- ウコギ科の植物は、日本には7種が生育しており、山地にはヤマウコギ、ケヤマウコギ、エゾウコギ(北海道)などが自生しています。
- 米沢で栽培するヒメウコギは中国原産の植物で、最初は薬用として日本に持ち込まれ、庭や生け垣に植えられました。古くは平安時代の「延喜式」(905~27年)に、ウコギの皮(樹皮、根皮)が日本各地から朝廷に献上された記述があり、薬用に使われたようです。
中国原産のヒメウコギ
- 米沢のウコギは中国原産のヒメウコギがほとんど。平安時代より漢方の強壮剤として使われ、また、茎にとげを持つことから、戦国時代の城下町では生垣として盛んに植えられました。 米沢では、上杉鷹山公が垣根や、旬の野菜として食することを奨励し、古くから暮らしの中にありました。
 ヒメウコギは落葉低木で、大部分は雌木で、とげが少なく葉も軟らかです。中国では古くからヒメウコギのことを五加(ウーコ)と呼び、日本ではそれに木をつけ、五加木(ウコギ)と呼ぶようになりました。日本最古の本草書(918)にも記されていることから、相当古い時代(千余百年前)に日本に渡来してきたものと思われます。ヒメウコギはヤマウコギやエゾウコギなどに比べ食用に向いており、またそのトゲは、敵の侵入を防ぐ目的で屋敷の垣根として戦国時代は盛んに植えられました。
ヒメウコギは落葉低木で、大部分は雌木で、とげが少なく葉も軟らかです。中国では古くからヒメウコギのことを五加(ウーコ)と呼び、日本ではそれに木をつけ、五加木(ウコギ)と呼ぶようになりました。日本最古の本草書(918)にも記されていることから、相当古い時代(千余百年前)に日本に渡来してきたものと思われます。ヒメウコギはヤマウコギやエゾウコギなどに比べ食用に向いており、またそのトゲは、敵の侵入を防ぐ目的で屋敷の垣根として戦国時代は盛んに植えられました。
- ウコギ科の植物には、タラノキ、コシアブラ、ハリギリ、チョウセンニンジン、トチバニンジン、ウドなどがあります。これらの植物は今、食品や漢方ブームで注目されているものが多いようです。
城下町米沢の歴史的遺産
 江戸時代の清良記(1629~76年)には四月野菜に五加の名があり、葉を食したことがうかがわれます。更に農業全書(1697年)には園籬(そのまがき)に通ずる植物10種が上げられ、中でもカラタチ、ウコギ、クコが最適であることが記されています。貝原益軒の大和本草(1709年)にもウコギの葉を食べたり茶にしたり、また根で五加皮酒を作るなど有用性がわかり易く記されています。
江戸時代の清良記(1629~76年)には四月野菜に五加の名があり、葉を食したことがうかがわれます。更に農業全書(1697年)には園籬(そのまがき)に通ずる植物10種が上げられ、中でもカラタチ、ウコギ、クコが最適であることが記されています。貝原益軒の大和本草(1709年)にもウコギの葉を食べたり茶にしたり、また根で五加皮酒を作るなど有用性がわかり易く記されています。
- 織田信長の時代、各地の城下町にウコギ垣がありました。米沢のウコギ垣は、伊達や蒲生時代にさかのぼるのか、それとも米沢開発の恩人、直江兼続公時代に入ったものか明確ではないようです。それとも米沢藩初代上杉景勝公が会津若松から移し植えたものか、その解明は今後の課題です。
鷹山公とうこぎ
- 上杉治憲(鷹山)公時代の天明3年(1783年)に刊行された飯粮集には、「はを用ゆ也、いつれも差合なし、根常ならさるかてにあたりたるときハ、うこきの根をせんし半分につめのむへし」「うこぎ気味辛温無毒、葉を用ゆなり」などの記述がされています。19年後に出版された有名な「かてもの」にはその名が出てきません。かてものは極力野外自生植物に精選されています。このことから鷹山公時代には既にウコギ垣が米沢城下にあったと推測されます。うこぎは、米沢にとって歴史と伝統をもつ由緒ある植物であり、質量共に日本一であると推定されます。なぜ、このようになったか、三つ条件が考えられます。まず米沢の気候風土がウコギの生育に適していること、次に米沢人は昔からウコギ垣を辛抱強く作り、ウコギを食べ続けて来たこと、更に鷹山公がウコギ垣を推奨されたことなどです。